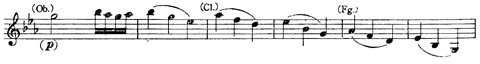29歳にしてロサンゼルスフィルの音楽監督になったグスターボ・ドゥダメルの就任記念演奏会と彼が共に育ったシモン・ボリバル・ユース・オーケストラの演奏会の録画を見る。シモン・ボリバル・ユース・オーケストラを指揮するのはアバド。 ドゥダメルはいうなれば雑草育ち。ベネズエラのスラム街の子たちに楽器を与えて犯罪や麻薬の誘惑から守ろうというエル・システマという音楽教育で育った。今や破竹の勢いで彼の名は世界に知れ渡りつつある。 エル・システマについてはドキュメンタリ番組で見た。アメリカのスラム街の子供たちをカーネギーホールまで導いた実話をもとにした映画「ミュージック・オブ・ザ・ハート」の世界に近いか。日本の才能教育(スズキ・メソッド)も音楽を社会教育のため手段の一つと位置づけている。子供たちに音楽を教えることは社会教育の普遍的な手段の一つなのだろうか。 > わたしがこの国を訪れて、いつの瞬間にも感じたことは、よりよい世界への心の要求が示されていたことでした。とくにわたしに強い印象を与えたのは、人生のもっとも高貴なものに対する追求でした。 この言葉は今にしてみれば、高度成長期まっただ中の日本の光景にこそふさわしい内容だったといえるだろう。今カザルスがエル・システマを見たらどういうだろうか。 |
|
ドゥダメルは何となく映画「アマデウス」でモーツァルトを演じたトム・ハルスに似ていて、映画の中のアマデウスがかもし出すように音楽も破天荒の天才。クライマックスへ向かってのあんなアッチェランドで聴衆を陶酔できる指揮者は彼を除くとフルトヴェングラーしかいないかも。サンバやマンボをドイツ音楽持ち込むなとか、ケチをいろいろ付ける連中はいるだろうが、あの若さにあふれた熱気の前には文句も吹き飛ぶ。 小澤征爾だってかつては欧米から見れば雑草育ちの一人だったかも知れない。その後成熟した日本を尻目に時代はベネズエラを含むBRICSが引っ張っていくようになってきたのだろうか。バーンスタインから小沢、そしてドゥダメルという流れが見えてくる。 映像で見るウォルト・ディズニー・ホールはとても大きなホールだ。音響設計はサントリーホールも手がけた日本の永田音響設計。聴衆の中に俳優のトム・ハンクスが写っていた。 |