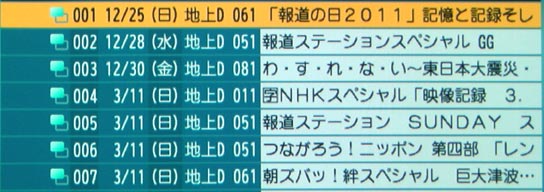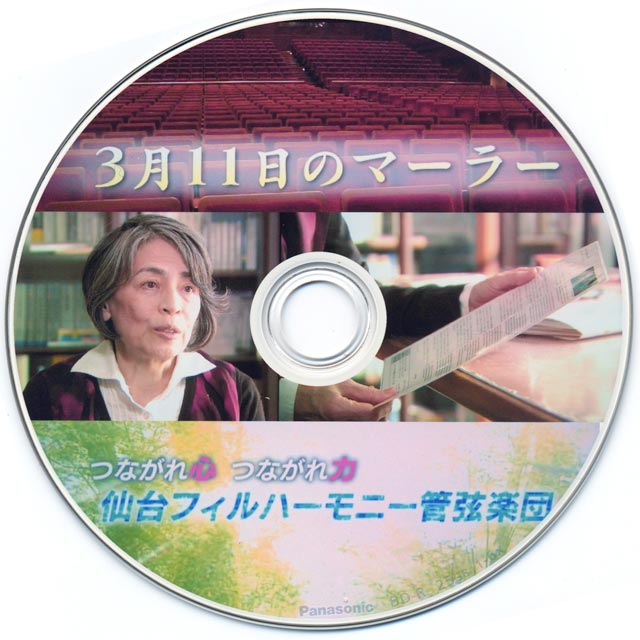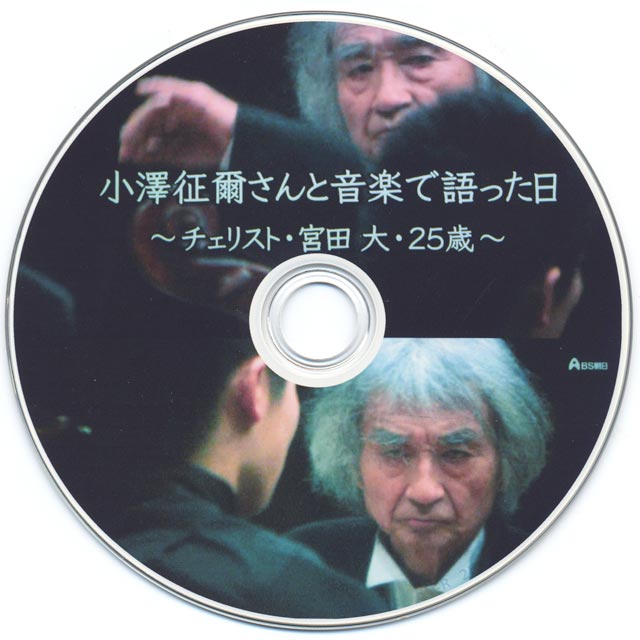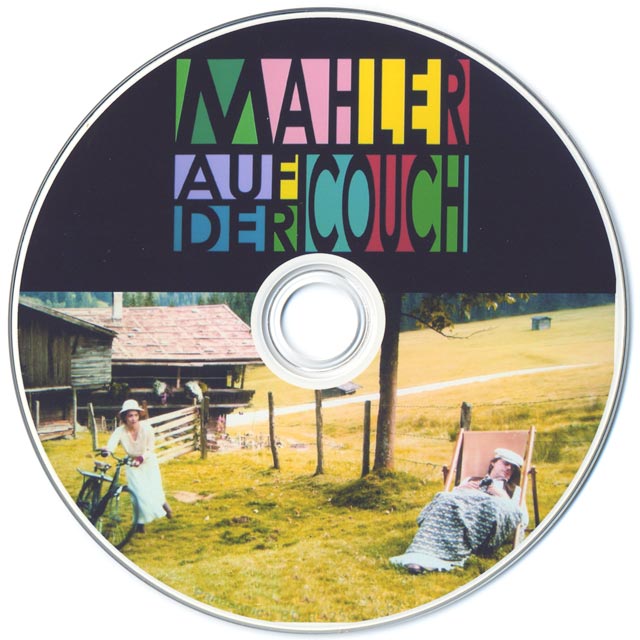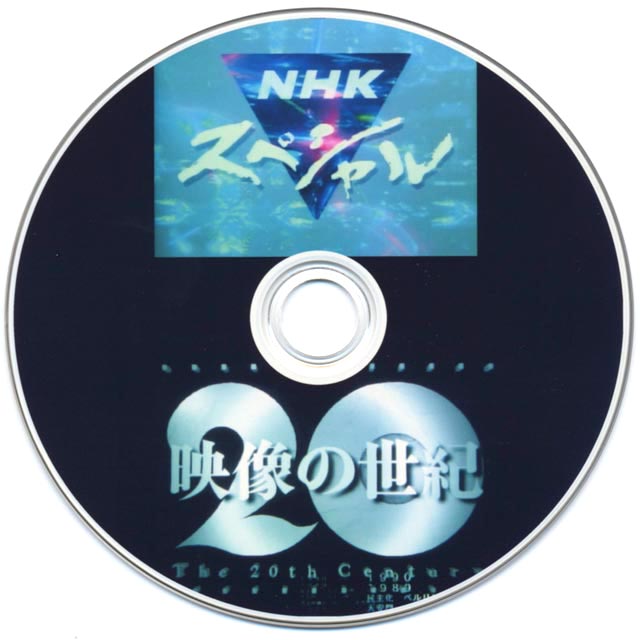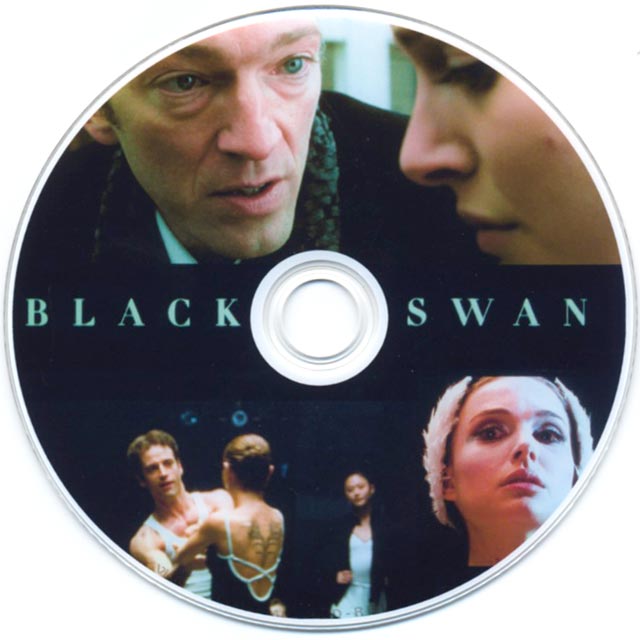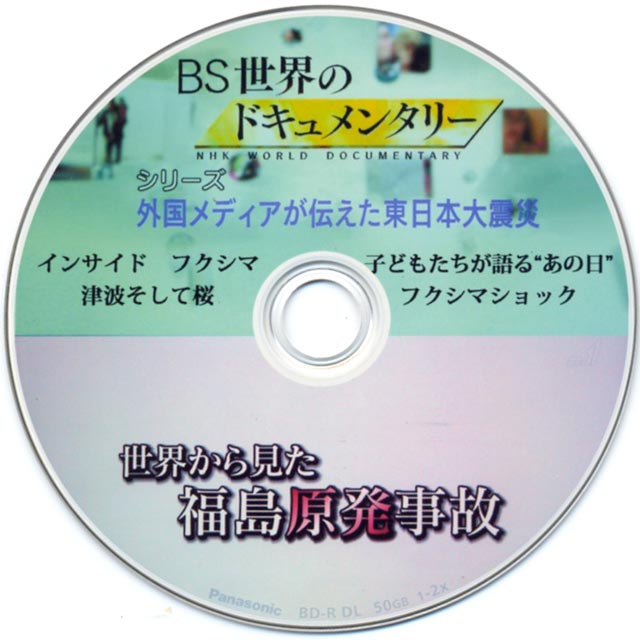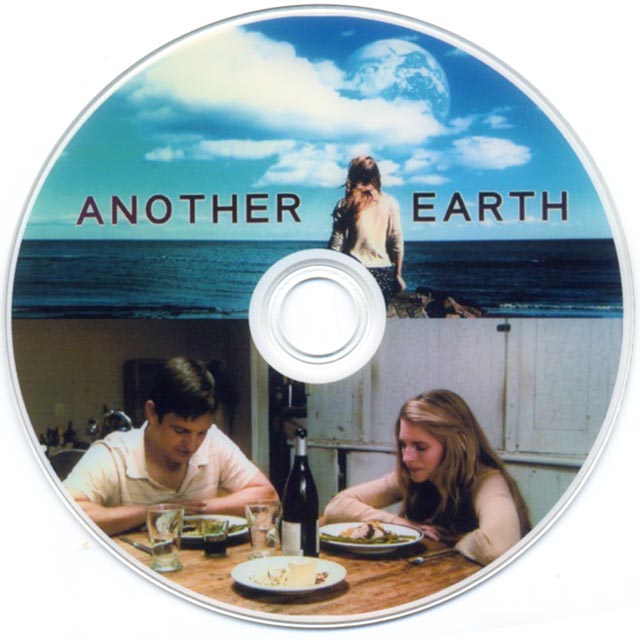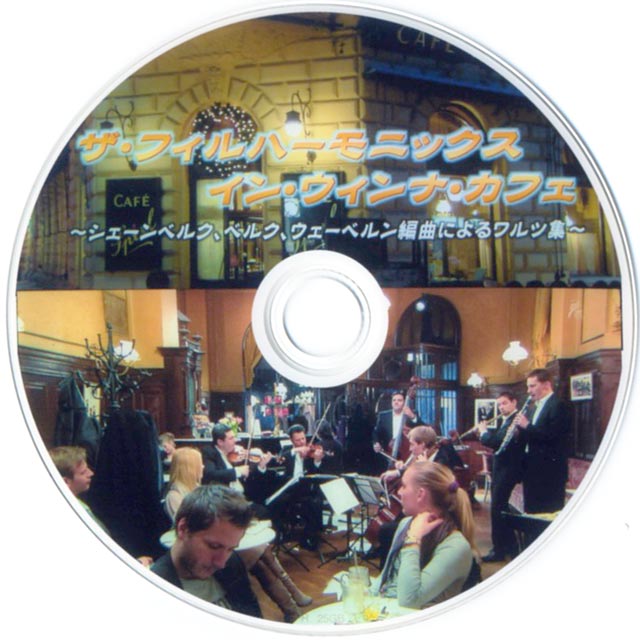この映画(原題は The Soloist)の原作はロサンゼルス・タイムズの記者スティーヴ・ロペスによる実話。邦訳も出ている(入江真佐子訳・祥伝社)。ジュリアード音楽院で学びながらも(映画ではチェロだが実際はコントラバス)統合失調症で中退し、ホームレス生活をしている男との関わりを描いた物語。 |
 |
手をさしのべようにも心を開かない彼、期待を持たせたかに見えて裏切られる現実・・・。愛と葛藤の日々は相手が心に障害を持つことに端を発しているように表向きは見えるのだが、意思の疎通を欠くこと自体は誰もの日常にあること、それが極端に現れたに過ぎないのである。根底には自己と他人との関係はいかにあるべきかという普遍的な問題が横たわっている。 映画では「エロイカ」を中心にしてベートーヴェンの音楽の断片がいろいろ出てくる。締めくくりに出てきたのは「第九」の第三楽章。ハッピーエンドとはいえないこの映画に「第九」の第三楽章が使われたことは「第九」に対するひとつの見解にもなっていると思った。 「第九」の終楽章は友愛と連帯(今の日本の状況では「絆」か)を歌いあげたいわば祝祭の音楽。ここだけしか聴いたことがない人も多いけれど、ベートーヴェンの音楽を愛している人ならば、この交響曲に「苦悩の第一楽章」、「闘争の第二楽章」、「愛と安らぎの第三楽章」というように、「歓喜の歌」へ向かってのストーリーを描きながら聴く。 では、ベートーヴェンは最後の交響曲において自身の結論を出したのか、というと異論はいろいろあるだろう。「第九」の終楽章は有名だが、その前の三つの楽章に比べて深みがないとはいろいろな人にいわれていることだ。取って付けたような感じさえする。歌われる歓喜はベートーヴェンの憧れではあったかもしれないが、作曲者自身が実際に到達した世界とは異なる。 映画のことに戻るが、「手をさしのべようにも心を開かない彼、期待を持たせたかに見えて裏切られる現実」とは晩年のベートーヴェンを煩わせた甥のカールに重なりはせぬか。それでもThe Soloistの作者は結論を得る。著書の最後の方に「わたしが救いたいと思ったこの男性が、わたしが彼のためにしたのと同じくらいのことをわたしにしてくれたといっても過言ではないだろう」と書いている。ある「悟り」があったのだ。第三楽章の調べはそこに結びつくのだ。 苦悩に始まるけれど歓喜へ一直線ではないベートーヴェンの一面をこの映画が照らし出してくれた。 |