交響曲月評
ショスタコビッチ 交響曲第5番≪革命≫ 小泉変一郎指揮 永田町管弦楽団
鳴り物入りの派手な宣伝で話題になったディスクだ。「これこそ本物、これを買わないクラシック・ファンは頭が保守的だ」といわれて買ってしまった人も多いだろう。
しかし、派手な宣伝自体が問題がある。まず、「革命」と標題を付けるのがおかしい。作曲者のショスタコビッチによって付けられたものではない。初演の日が何かの革命記念日であったからとかこじつけられているが、この標題は「運命交響曲」同様、あとになって「商売上」付けられたに過ぎない。作曲者にとっても不本意かも知れない「革命」という呼び方をうまく利用して、何か新しいことをやっているのだという印象を鳴り物入りで宣伝したのは、さすが小泉流、うまい。
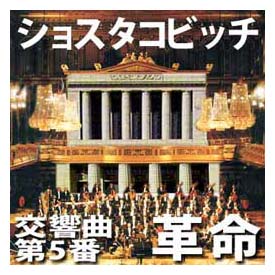 演奏は例によって歯切れのよいものだ。明快なアクセント、率直な表現は定評のあるところ。しかし、これまでも指摘していたことであるが、長いフレーズとなると意味不明、はぐらかされたような感じになり、薄っぺらな表現になる。年季の入ったリスナにはもの足らないのではあるまいか。 演奏は例によって歯切れのよいものだ。明快なアクセント、率直な表現は定評のあるところ。しかし、これまでも指摘していたことであるが、長いフレーズとなると意味不明、はぐらかされたような感じになり、薄っぺらな表現になる。年季の入ったリスナにはもの足らないのではあるまいか。
永田町管弦楽団は今回の録音に際してアンサンブル能力に欠ける団員を多数リストラし、新団員を公募した。新団員を加えた大編成の響きはまだオケになれていないゆえのバランスの悪さが散見されるものの、迫力満点。
今回のディスクは予想外の売れ行きで、一部では品不足が伝えられている。宣伝につられてつい買ってしまったけれど、少しもよくなかったという方は返品して手に入らなかった方に回して欲しいというのがディスク管理委員会の通達である。
[録音評] 9月11日厚生年金会館で録音。編成の大きさに対して左右の広がりが今ひとつだ。演奏者あるいは指揮者の指示によるのかも知れないが一部の楽器がクローズアップされる。派手さはあるが音楽的には疑問な箇所が多い。 |
