■岡崎 光治 歌劇「鳴砂」飯田哲成指揮 仙台交響楽団 |
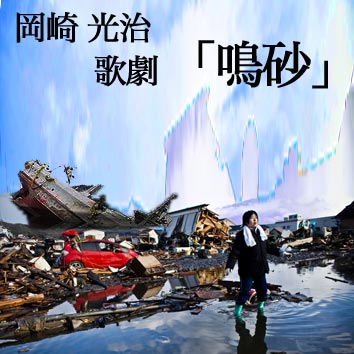 |
原発事故を受け、戦後日本がたどった文明を問い直すあまたの評論が雨後の竹の子のように出てきている。しかし、冷静になって振り返れば、この文明の陰を象徴するような危険と権力がどろどろと溶け混ざった装置に対する危惧はその登場と共に語られてきたのだ。今になって再発行される書籍も多い。 |
2011年秋号より 全ページ(PDFファイル)はここから
■岡崎 光治 歌劇「鳴砂」飯田哲成指揮 仙台交響楽団 |
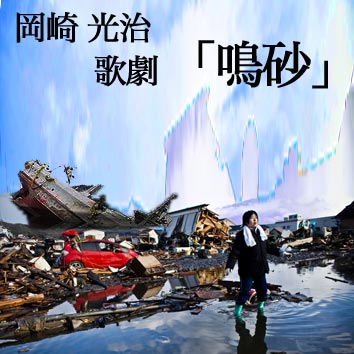 |
原発事故を受け、戦後日本がたどった文明を問い直すあまたの評論が雨後の竹の子のように出てきている。しかし、冷静になって振り返れば、この文明の陰を象徴するような危険と権力がどろどろと溶け混ざった装置に対する危惧はその登場と共に語られてきたのだ。今になって再発行される書籍も多い。 |
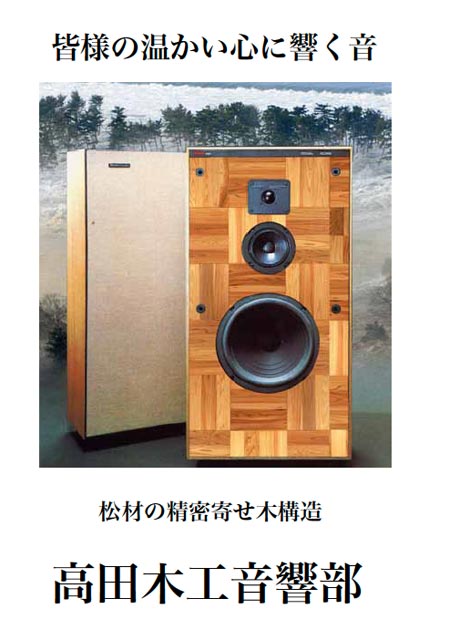
全ページをPDFファイルでお読みになりたい方は下の画像をクリック
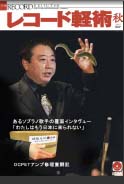
2011年4月号を見る 2012年4月号を見る バック・ナンバーの先頭に戻る パロディ誌「レコード軽術」の先頭に戻る