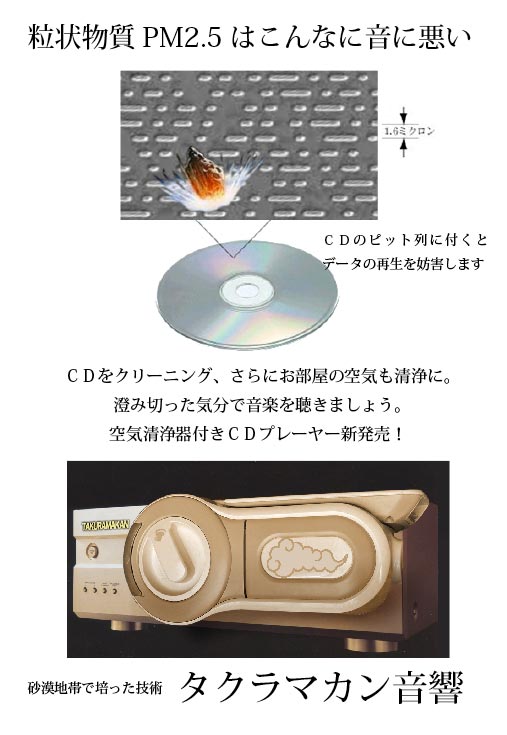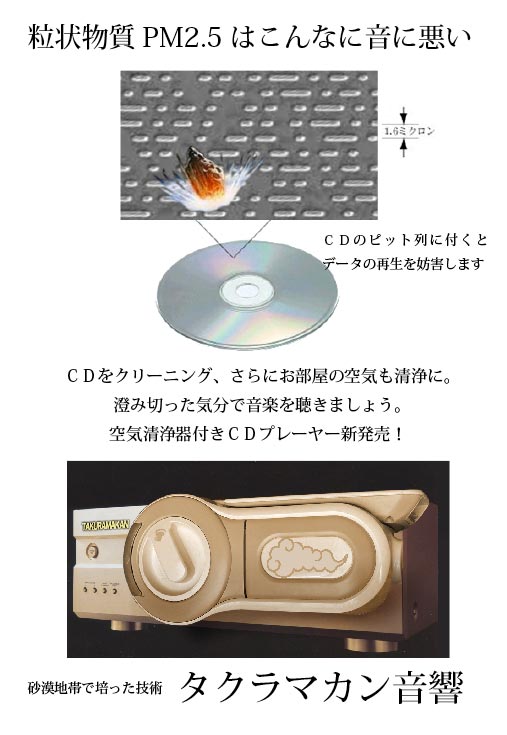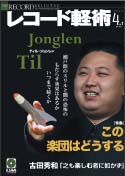古田秀和 これも楽しむに如かず
桜の季節になると必ず通る小道がある。歩いて十分ほどの間に桜の木は数本ほど。私は木について詳しくないので良くわからないが、ソメイヨシノではない山桜の一種なのだろうか、華やかさにはちょっと欠けるかもしれないが、それぞれに美しい花を咲かしている。
一番大きな木のそばには、近くの農家の人が残したのだろうか、作りかけの東屋といったらよいか、物置を改造しようとして中断したような小屋が建っている。そこには腰を下ろす場所もあってそこから見渡す風景が素晴らしい。コンクリートの近代的な施設とは正反対の、朽ち果てた誰が作ったかわからない、それも未完成な建物なのに、なぜか入るとホッとしたような気分になる。小屋を作った人はどんなものを建てたかったのだろうか、今どうしているのか、年々朽ち果てていくのがわびしい。
人々は生きている間にたくさんのものを残す。いくつかは創作物として作者亡き後も多くの人から賞賛され続ける。しかし、その数は人々の努力と試行錯誤の跡ーーー私の好きなこの小屋も含めてだがーーーのほんの一部にすぎない。運良く生き延びることができても、ーーー滅び去った文明の跡を見るがよいーーー人々の営みの狭間でどういう運命をたどるかはわからない。人間の創造物とはそもそも儚いものなのかもしれない。しかし、努力と試行錯誤があった事実は容易に消し去ることはできないし、それすら失われたら進歩の跡をたどれなくなり、向上の手がかりを失う。
1820年頃、シューベルトはたくさんの曲を書きかけで放棄した。シューベルトは作曲家として歌曲ばかりではなく交響曲の大作にも取りかかりたいと願っていたが、それをなすには自身の枠をはみ出さねばと、悩んだ末のことだったのだろう。
シューベルトの弦楽四重奏曲で第12番とされるハ短調の曲は第一楽章は書き終えてあるものの、第二楽章はスケッチのみであり、始めの部分で終わっている。それゆえ《四重奏断章》 と今日呼ばれている。全楽章の完成には至らなかったが、新境地を切り開かんとするシューベルトの気迫が溢れている。室内楽の至高の作品と讃えられているベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲が作曲される前、若きもう一人の天才がこのような作品を残していたとは驚く。
創造の行為は未完におわっても、結果が思わしくなくても、忘れられないようにしたい。もし「負の遺産」と呼ばれるものになっても、その陰にはたとえ止むに止まれずした結果であろうとも、無名の人たちの涙ぐましい努力があるのだ。同じことを繰り返してはいけないというメッセージとして伝ていこう。
(編集部より)本稿は故・古田秀和氏と親しかった某氏から遺稿としていただきました。感謝に堪えません。 |