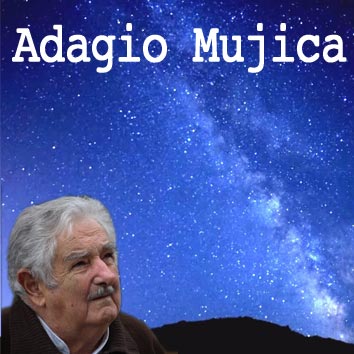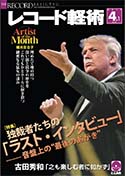訪れが遅かった春を埋め合わせするようにここ二、三日急に気温が上がり、桜の開花も進んだ。花のもと、ふざけあう子どもたちの歓声が懐かしい音楽に出会ったように響く。我々は今年の開花は早いとか、梅がまだ咲いているとか、経験との比較が感想に入ったりするけれど、幼い子にとってはすべてが新しい。次から次へと変化する季節の移ろいに幸福な未来の予感を当然のこととして重ね合わせているに違いない。
幸福な未来の予感という語句を使った忘れられない文がある。一部を紹介する。
近頃はことあるたびに自分が死ぬときが来たと感じさせられます。今やまさに終わろうとしているのです。私は自分の才能を十分使わないうちに死んでしまうのです。それにしても人生は美しかったし、私の仕事は幸福な未来の予感につつまれて始まりました。
これは、モーツァルトが世を去る三カ月前、絶筆となる「レクイエム」の作曲中に書いたとされ、後に偽作と判明した宛先なしの手紙の文である。モーツァルトファンならでの早世を惜しむ気持ちにあふれていて、偽作であることが惜しいほどの美しい文章であることには異論はないだろう。
中でも、「幸福な未来の予感」という語句にはモーツァルトの若い頃のはつらつとした輝きを持つ作品群の特徴が端的に表現されているではあるまいか。しかし、世を去る1791年に作曲されたクラリネット協奏曲やピアノ協奏曲27番では表現の対象はこの世の雑事を超えた美の世界へと移る。「幸福な未来の予感」は「天上への想い」となる。
人間の記憶の仕組みはよく分かってないし、解明尽くされることはないだろうがーーー実はそう願いたくもあるのだがーーー予感なるもの、自らの経験と実績でこの先起こる事柄を論理的に予測した結果に基づいていると言い切ってよいのだろうか。「幸福な未来の予感」や「天上への想い」はどのようにして生まれるのだろうか。
臨死体験なるものが少しは研究されている。病気や怪我で苦痛の極致にあるときでも最後には脳にある物質が供給されて苦痛が取り去られ、安らかな表情で死を迎えるのだという。このとき、脳に供給される物質は予感として「天上への想い」をも促すのだろうか。それは前にも述べたように、解明尽くされることはなさそうだが。
個々の一生は自分の意志では逆らえない運命のようなものによって決まっているのなら、日常の繰り返しはいつか終わらされる。忍び寄るこの世のものでない世界の予感。モーツァルトに限らず芸術家のラストメッセージはかくなる予感から生まれたものかも知れない。
芸術は作者亡き後も残る。作者の名も小惑星の名前になれば人類よりも、もしかしたら地球よりも後まで存続する。ただ、政治家や宗教家の名前は死後百年以上経ってからでないと命名できない。国際天文学連合の規則だ。何百億年という時間スケールで空を眺めている天文学者の考え方に救われる。星になれる政治家は何人いるだろうか。
本稿は故・古田秀和氏と親しかった某氏から遺稿としていただきました。
感謝に堪えません。(編集部)