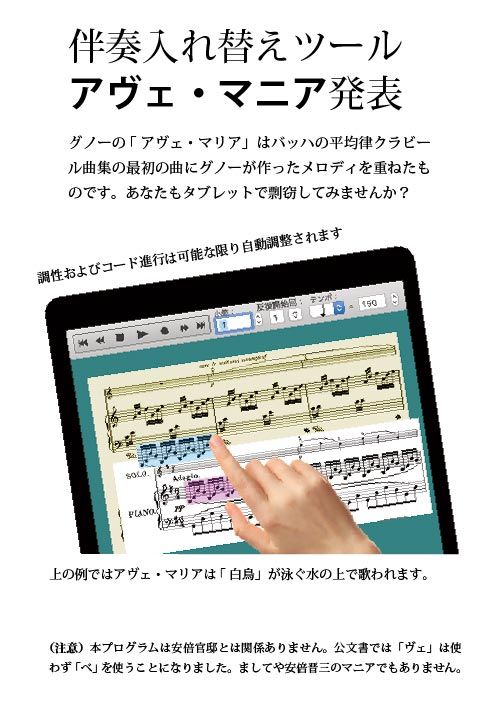激論! 「やってる感」だけでいいのか
マーラーやブルックナーなどの長大な曲を聴衆にいかにして飽きさせずに演奏したらよいか永田町管弦楽団始めとする主要なオーケストラの指揮者が集まって討論会が行われた。司会は望月磯子さん。予定では永田町管弦楽団からもう一人菅偽偉氏が出席する予定だったが都合でネット経由の参加となった。

司会(望月)
ここにいらっしゃる方のうち一番長く常任指揮者を務めてられるのは永田町管弦楽団の安倍さんです。長い曲をやる際の心構えは何でしょうか。
安倍 ええとですね、演奏に緊張感があれば聴衆を飽きさせないことにつながっていきますので、最大限の努力をしてきたつもりでございます。
司会 それは当然ですね。伺っているのは飽きさせないための秘訣は何でしょうかということですので、もう一度お答え下さい。
安倍 演奏する曲はそれぞれ違いますので、個々の問題に対してはお答えできません。
司会 あのですね、壇上にいらっしゃる指揮者の方々も、会場に来ていただいた皆さんも、知りたがっていることは、音楽の専門家はどのように楽曲に向かい合い、何を伝えたいのかです。それが分かれば演奏会に足を運ぶ人も増えることでしょう。例えばブルックナーではいかがですか?
安倍 長いのは飽きますよ。肝心なのは冒頭。何かすごいことが始まると印象づけておき、最後にもう一度本気でやれば聴衆は付いてきます。あのね、心のときめきは75秒と言いまして、序奏から第一主題に移って75秒も経過すればほとんどの人は第一主題の始まりがどんなだったか憶えてませんよ。
司会 そのような期待だけ持たせて結果知らずでは「やるやる詐欺」ではありませんか。
安倍 まさしくご指摘の通りでありまして、それを避けるために再現部や変奏で解釈を変えるようにしています。「三本の表現」と呼んでいます。
司会 要するに、その変化が続くことで盛り上がる結末に至らずとも「やってる感」が出て飽きられないということですね。
枝野 途中から失礼。安倍さんのやり方では音楽に込められたストーリーや理念はどうなっちゃうんですか。私なら基本的に何の変化もない曲をうんざりしながら聴いているだけですね。
安倍 そうはおっしゃるけれど、あなたの演奏会でどれ程お客が来ましたか?理念を語っても客がいないのでは話になりませんよ。
間随 うちは客に合わせ臨機応変。筋を通すことより音楽に維新をです。
志位 筋を通す事が悪いという風潮の中で、我々はぶれずにやって来たからここまで続いたのです。それが王道だと思っています。
以後も議論は続いたが、会場の使用時限に迫った結果、司会の制止に従って討論会はお開きになった。