今月の三枚目 古田秀和
ブラームス 弦楽六重奏曲第一番
ウィンテルSQ・アキア(Va)・マッキントッシュ(Vc)
百年前の四月三日の朝、ブラームスは六三年の生涯を閉じた。芸術家の作品は後期になるほど完成度が高いといわれることが多く、ことに晩年のものは作者の人生の総決算として、特別の位置を与えられることも多い。ブラームスの場合は「四つの厳粛な歌」をはじめ、クラリネット五重奏曲やクラリネット・ソナタなどである。
これらは、いかにもブラームス的な−こう簡単にいい分けてしまえるものではないけれど−内省的で、孤独で、安らぎの裏には諦めの陰がつきまとう、奥の深い音楽である。ブラームスの音楽を語るとき、これらの作品は欠かせないが、ほかにも素晴らしい作品がたくさんある。
芸術家の作品はいつも若い頃は稚拙・荒削りで、後期になって円熟して価値がでてくると直線的に片づけられるものではない。若さ故に生まれる躍動・夢・情熱の表現は捨てがたい。ブラームスという人は何となく早くから老成していたかの印象を持たれがちだが、今回取り上げる「弦楽六重奏曲第一番」は二十代の、ようやく作曲家として評価され始めた頃の輝きに満ちた曲であり、演奏も、ブラームスの若き側面を押し出している。
第一楽章がことによい。早めのテンポでよく歌い、展開部の盛り上がりも上滑りしない。アレグロ・マ・ノン・トロッポ。このテンポは、新緑の林を野を、次から次へと変わる景色にわくわくしながら息をはずませて進む時の胸の鼓動だといったらよいだろうか。いまの季節にはよく似合う。第二主題がチェロからバイオリンへと渡されていくあたり、まさに汗ばむような日差しと青い空、青春の夢いっぱいという、幸福な気持ちにしてくれる。
しかし、ブラームスの音楽の魅力の一つは、このような場合でも単に青春万歳と音楽を終わらせないところにある。たとえば展開部に出てくる、この突然のハ長調ののコードと、それに続くたどたどしい短調の旋律は何だろう。
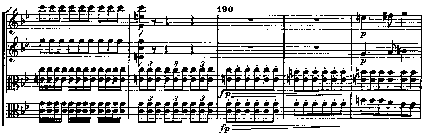
ぼくには才能がある、良き隣人もいる、なのに、この孤独はなぜ?むせかえるような緑の草原の真ん中で、全身に陽をいっぱい浴びつつも、寂しいのはなぜ?
そんなブラームスの息づかいがうかがえはしまいか。
若いといっても当時ブラームスは二七歳。大学教授の娘アガーテとの愛も実を結ばず終わった。以後ブラームスの愛はクララ・シューマンへと向かうが結局独身を通す。このハ長調のコードはブラームスの青春の幕引きの音ではなかったか?ブラームスの音楽の光と陰はこのような体験を経て生まれ、奥深くなっていったのだろう。
この演奏を聴くとき、これから恋多き人生を送るかもしれない人は、いや、淡い思い出が一度あっただけの人でも、いろいろな人生のひだについて思いを巡らせるに違いない。新緑を窓辺に見ながら聴くにはお奨めの一枚である。 |