タルコフスキー その1
作曲家や演奏家の中から一人を選び,その人の全作品を集めたい,そう思ってコレクションを始めた人も多いだろう.ぼくが高校の頃文通していた人は,「ぼくは一生かかってもフルトヴェングラーの全録音を集めようと思っています」と書いていた.文通は途絶えてしまったが,30年後,その人はフルトヴェングラーの録音の研究者として押しも押されぬ人となっていたのには驚いた.
フルトヴェングラーは特にそうだが,ほとんど全部というところまでコレクションが集まるとその先へ進むのが極めて困難になってくる.疑問盤とか,あるかどうかも不明なものばかりになってくるからだ.ぼくにはそのような困難を乗り越える根気はとてもない.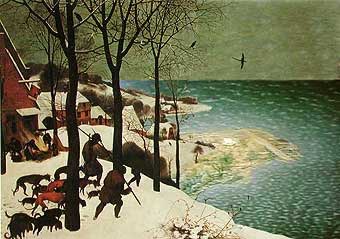
それでも唯一「全作品」をそろえているのが旧ソ連の映画監督・タルコフスキーの作品.学生時代の作品や演出したオペラを含めても10作しかない.ぼくに出来るのはこの程度.
タルコフスキーは旧ソ連末期に西側に亡命し,50代半ばで世を去った人である.「映像の詩人」と評されるが,奥が深く難解.もっとも知られている「惑星ソラリス」にしても原作はポーランドのSF作家スタニスラフ・レムの哲学的な作品で,SFを「スターウォーズ」のごとき「宇宙チャンバラ」としか見ていない人は面食らってしまうだろう.かつての東側では,体制批判の文学の代わりに哲学的なSF小説が盛んだったのだ.高校の頃「SFマガジン」などでよく読んだものだった.
タルコフスキーの作品の思索的な背景に常にあるのはバッハの音楽と聖書である.これらに関心のない人は見てもわからないとはいわないが,タルコフスキーの作品はたくさんの人にもてはやされる性質のものではないことは確かだろう.長大で思索的な作品ばかりを残し,それもたった8作.旧体制の善し悪しは別として,こういう芸術家はもう出てこないのではあるまいか.
|



