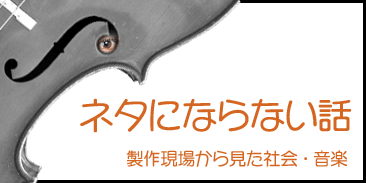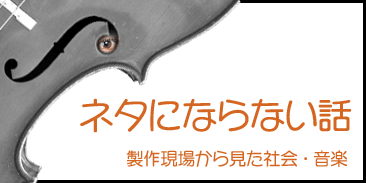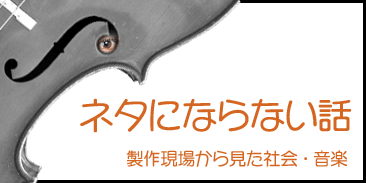 |
「レコード軽術」の発行は年2回.毎月出せという人もいるけれど、そんな能力はありません.第一、ひと月ではそんなに面白いことがあるわけない.この商業ベースにならないやり方はずっと続くと思います.
ここではパロディのネタにはなりそうもない話題を中心に気が向いたときに書くことにします.次の号までの退屈しのぎ?
|
2012.12.6 下記のテーマのうち「アインシュタイン」、「遺したいもの・伝えたいこと」および
「教育と文化」に後日談などを加筆しました。
いわゆるFAQ 読者さまざま スノッブ 家内工業とDTP オーディオ 登りつめるにはバッハ
自慢にならない話 コンピュータ 鑑賞と表現 デジカメ アインシュタイン タルコフスキー
遺したいもの・伝えたいこと ケチと浪費 言ってはいけない 内輪の話・よその話 果てしなき流れの果てに
読者はこうしたもの 論理の世界・感覚の世界 話の糸口 夢と現実 自分の価値観・他人の価値観 なめるな!
永田町管弦楽団 教育と文化 コスモス
両論併記、そして… その1
ある歴史に残る音楽家についてのサイトを運営している人がいる。ディスコグラフィーはもとより、その真偽についての報道を検証したり、豊富な資料で一杯である。特にファンでなくても、調べ物をするとき便利で信用があり、ときどき読みに行く。
しかし、敬遠したくなることもある。それは主宰者の日記だ。音楽とは関係のない政治の動きを取り上げて「これには怒りを感じる」という。政治家や官僚の汚職についてなら、ほとんどの人がその怒りを同感できるのだが、彼の主張は思想的なもので、テーマによりけりだが、心情を同じくする人は世論調査をしてもせいぜい1/3ほどもいるだろうか、要するに、「過激」に近いのだ。「これには怒りを感じる」というのを読んで「こんなことを書くとは」と怒りを感じる人も多いはずだ。
もちろん、個人の日記に何を書いてもいいのだけれど、音楽のことをやり取りしたくてアクセスしたのに、自分と異なる政治信条を押しつけられてはたまらない。政治の話はほかの所へ移すか、「こういう考え方もあるけれど、私はこう思う」とひとこと付け加えればずっと近づきやすくなる。
音楽家に限らず、種々の創作活動をされている方々はそれぞれ政治的スタンスを持っている。しかし、特定の団体のプロパガンダ活動でない限り、自身の表現したことはより多くの人に理解してもらいたいに違いない。芸術はより普遍的なものである。
|
両論併記、そして… その2
放送法では、報道に対するコメントは両論併記することが求められている。一方的な世論の扇動を招かないようにだ。「こういう見方もあるし、ああいう見方もある」という表現が出来るには、対立する意見の双方についてよく知らなければならない。政治に限らず日常のいろいろな場面でこの能力が試される。
たとえば、他人を責めたり叱責する際、いきなり「アンタのした事はどうのこうの」と切り出すより、「面倒なことに手間をかけてもらって悪かったが」とか「いつも嫌な顔ひとつ見せずにやってもらって感謝しているのだけれど」とか、さらに「連れ添ってここまで何十年もやってきたのは、君の明るくまっすぐな心があったからだけれど」とかのことばで切り出せば、相手をぐっと引き込むことが出来る。それが出来るには、たとえ敵意のある相手であっても長所と短所をよくつかんでおかねばならない(と、書きながら、本人はまったく下手だけれど)。人間的な修練が必要とされるのだ。 |
両論併記、そして… その3
パロディは主張が目的ではないから、「こういう考え方もあるけれど、私はこう思う」ではなくて、「こういう見方も変だ、ああいう見方も変だ」と突き放し、高見の見物をしているように双方を皮肉るものでありたいと思う。もし、どちらかに偏るとしたら、それを心よしとしない人たちの主張に耳を傾けてないからだ。そして、そういう側に属している読者を失うことになる。つまり、パロディでなくなる。
たとえば、こんなのは対立軸が何も表現されていない単なる語呂合わせだから、愚作だ(03年春号)。
|

政治問題の中から音楽との接点を失わず、かつ対立する主張のどちらをも茶化すことが出来るネタを見つけるのは、とても難しい。 |
パロディ誌「レコード軽術」の先頭に戻る