新譜月評・声楽曲
■ショスタコービッチ オラトリオ《森の歌》 森野中亀 指揮永田町管弦楽団 石川市民コール
ショスタコービッチの《森の歌》は複雑な経緯を持っている。まず、作曲者が共産党の批判にさらされ、やむなく?(これについては今だ真相は不明)書いた体制迎合ともいわれている作品であること、初めその中にスターリン礼賛の歌詞があったが、後のスターリン批判によりその部分が書き改められたことである。
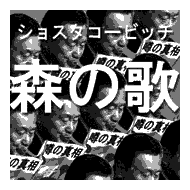 作曲後半世紀を過ぎ、東西冷戦も終わったいま、優れた声楽作品の一つとして歌い継がれるようになったのは好ましいことである。 作曲後半世紀を過ぎ、東西冷戦も終わったいま、優れた声楽作品の一つとして歌い継がれるようになったのは好ましいことである。
ここではアマチュアの合唱団が起用されている。メンバー個々の技量はプロの声楽家と比べ声量などでおよばないところがあるものの、表現力を買われ、プロの演奏団体と協演する団体も多い。
さて、近年コーラス・グループの平均年齢がとみに高くなってきてはいまいか。ここ20年くらいの流れを見てもアマチュア・オーケストラの数はひょっとすると10倍近く増えたのに、コーラス・グループは人集めが大変らしい。音楽嗜好の多様化はかねがねいわれてきているが、本質的なものを見落としてはいまいか。アマチュア・オーケストラが増えたのに、オーケストラを聴きに行く若者が激減というのもおかしいことだ。
それはさておき、この演奏からはのびのびした表現意欲が感じられない。歌詞も不明瞭。その理由の一つに譜面に釘付けになっていることがあげられる。関係者の話だと、何度注意しても1962年に改訂される前のスターリン礼賛の歌詞を歌う者がいて、そのような「失言」を避けるため、全員が譜面を見ながら歌うことになったという。
昔おぼえたことが抜けず、何度も繰り返すひとに時代の流れをつかむセンスがあろうか。合唱団のメンバーは指揮者とその側近が面談の上きめたという 。時代に即応できない柔軟性を欠くキャラクタという点では選ぶ方も選ばれた方も五十歩百歩だ。
[録音評]とうに音楽ホールとして使われなくなった日比谷公会堂での録音。乾いた響きは音楽から色彩を奪う。企画の古さを感じざるを得ない。ここが選択された経緯が不明。指揮者の故・崖渕牛三氏が予約しておいたのを「後を頼む」の一言で使ったともいわれているが、真相は不明。 |
